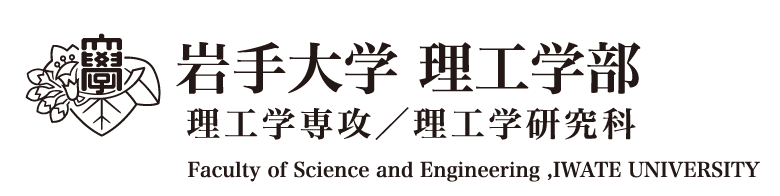理工系教育研究基盤センターについて
理工系教育研究基盤センター(以下、「基盤センター」と称す)は、平成28年度にスタートした理工学部の設置計画立案の過程で生まれた組織であり、設置の経緯と目的を以下に紹介します。
冒頭に、前センター長の船﨑先生による過去の説明の抜粋を掲載します。
『理工学部の設置に関する議論は、国立大学の改革の大きなうねりの中でスタートし、その具体については岩手大学全体の機能強化の施策の一環として構想されたものです。理工系学部の再編については、工学部を母体としつつ旧教養部の流れを汲む人文社会科学部(人社)に在籍する理系教員の異動や学長ポストによる理系教員を採用することにより実現するという方向性は平成25年度末には定まっておりました。ただし、当初から理工学部ありきで議論が進んでいたのではなく、工学部のままというシナリオもありましたが、新しい教育研究体制となることを学内外に指し示すには学部名称と学位の変更が必要であるという当時の工学部長、執行部の考えに基づき、多くの議論を経て岩手大学理工学部が誕生しました。
人社理系教員の異動が理工学部設置に重要な要因の一つではありましたが、それは単なる人の組織替えではなく、人社がそれまで担っていた専門基礎教育機能の多くを新たな理工学部が引き受けることを意味していました。過去の学部改組における経験を踏まえ、専門基礎科目を担うための組織を設置することが必要であることが学部内でもある程度の共通認識となっていたことから、専門基礎教育を担う組織の設置構想を学部に問い、最終的には全学に提案しました。それが、基盤センター設置の契機となっています。』
基盤センターには、従来の委員会方式では対応が困難でかつ新たな学部運営に欠くことの出来ない業務を担当する組織(部門)を設置しています。
理工学専門基礎教育部門
学部及び他学部の理数系共通科目の実施や運営を担っており、積み上げ方式の理工系専門教育での学生の学びを支える重要な役割を果たしています。
英語教育部門
理工学部の教育目標であるグローバル理工系人材育成に向けての学部内英語教育の強化を目的とした部門です。高校までの英語教育が大きく変化する中、全学の動き、他大学の動向調査などを踏まえながら、学部における教職員および学生の英語能力の向上のための取り組みを行っています。
特別プログラム部門
理工学部の4つの特別プログラム(地域協創ものづくりプログラム、地域防災・まちづくりプログラム、データサイエンス応用副プログラム、半導体人材育成プログラム)の活動を支援するための組織です。業務としては、各プログラムの入試対応などに加え、各プログラムの運営および予算確保などに取り組んでいます。
高大連携・接続部門
学部として、SSH、SPPなどに加え、理数科の課題研究、研究室へのインターンシップであるアカデミックインターンシップなどを通じて高校における理数科教育に協力していましたが、教員個人のレベルで対応していたため様々な弊害も生じ始めていました。そこで、この理数科教育への支援を組織的に行うことで高校と大学との連携を強化し、理数分野に関心を持った高校生の育成支援と、岩手大学理工学部への関心を高めるための活動を行うことを目的として設置されました。
入試・入試広報部門
入試に関する定量的調査とそれを踏まえた効果的な広報活動を企画することを目的とした部門です。入試委員会や広報委員会では実施が困難な他大学の動向調査など詳細なデータの分析などを行い、その結果を入試委員会や広報委員会等と共有しています。
教育改善部門
学部内における教育面でのPDCAサイクルを回すための重要な組織です。WebClassの活用促進、Webによる毎学期の授業アンケートとまとめ、その分析による授業改善に向けての助言、FD研修などを行っています.授業改善についての取り組みは、授業アンケートの結果に顕著に表れており、学部の教育の質の補償に大きく貢献しています。
グローバル研究者育成部門
平成29年度の理工学専攻設置時に導入された部門であり、専攻内の特別プログラムに相当するグローバル研究者育成プログラムを支援することを目的とした部門です。
以上、基盤センターと各部門の概要を紹介しました。理工学部における教育研究をいろいろな面で支えている組織であり、学部構成員の皆さんからの協力を得ながらより充実したセンター活動を展開していきたいと思います。
組織
| 理工系教育研究基盤センター | 部門 |
|---|---|
| 理工学専門基礎教育部門 | |
| 英語教育部門 | |
| 特別プログラム部門 | |
| 高大連携・接続部門 | |
| 入試・入試広報部門 | |
| 教育改善部門 | |
| グローバル研究者育成部門 |